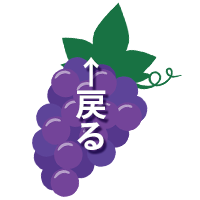「通信あけのほし」283号を発行しました
支援者向けニュースレター「通信あけのほし」283号(9月30日号)を発行しました。
最新号の巻頭言と館長挨拶を以下に掲載します。
第9回アフリカ開発会議 菊地功(きくち いさお)
石破首相が自民党の総裁辞任を表明され、来月には新しい首相に交代することになりました。1年足らずの任期でしたが、続投を求める声が与党以外から聞かれる珍現象もありました。その政治的意味合いを論じる知見はありませんが、任期中には、石破氏の政治家としての姿勢を象徴する発言がいくつかあり記憶に残りました。
その1つが、先日8月に横浜で開催されたアフリカ開発会議(TICAD)での発言です。 そもそもTICADとは何なのでしょう。外務省は国内向けに「アフリカ開発会議」と称していますが、英語略称の「T」は「東京」の頭文字ですから、本当は「アフリカ開発東京国際会議」です。今回が9回目です。第1回目は1993年10月で、そこでは「東京宣言」が採択されました。
「東京宣言」は、アフリカ支援の必要性を強調しつつも、援助だけではアフリカの問題が全て解決されることはないと指摘し、さらに援助のためにはアフリカ諸国の対応(民主化、良い統治等)が必要であることも指摘しています。その上で、アジアにおける経験をアフリカ開発に生かす可能性にも言及していました。アフリカ支援のお手本のような内容です。
つまりTICADとは、日本政府が音頭をとって、国連諸機関や世界銀行とともに、アフリカ諸国のリーダーや援助国の代表を一堂に集め、アフリカ開発のための諸課題を話し合い、よりふさわしい道を提示し、さらには国際社会にその実現を訴えようという場なのです。世界に知られるべき会議だと思います。
その閉会の挨拶で、石破首相は、「日本はアフリカの皆さんと共に笑い、共に泣き、共に汗をかきながら、アフリカが直面する課題の解決に1つ1つ取り組んでまいります。それはただアフリカのためではない、ただ日本のためでもない、世界のためであります」と述べました。さらに、ガーナにおいて黄熱病の研究中に亡くなった野口英世の言葉、「私は、皆様に何かを教えに来たのではない。皆様方から多くのことを学ぶために来たのだ」を引用し、「私たちはアフリカの皆様方から多くを学び、その成果をアフリカのために、そして世界のために、そして未来のためにいかしてまいりたい」と結ばれました。
謙虚に多くの人の声に耳を傾け、そこから学び、「ともに笑い、共に泣き、共に汗をかきながら」という姿勢こそは、利己主義と暴力に席巻されている現代社会に、いまだからこそ重要で必要な人間の生きる姿勢であると思います。
読書バリアフリー法第二期基本計画始動 館長 平井利依子(ひらい りいこ)
2019年(令和元年)に成立した読書バリアフリー法(正式名称は「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」)は、今年7月に第二期基本計画が策定されました。2025年から5年間です。
「通信あけのほし」では、2021年9月、12月、2022年4月の3回にわたり、評議員の佐藤聖一氏に「読書バリアフリー法」の解説をしていただきました。「読書バリアフリー法」は、全ての国民が読書を通じて文字・活字文化の恩恵を受けられることを目的としています。点字図書館は視覚障害者だけが対象でしたが、現在は視覚障害以外の障害の方々も対象です。公共図書館の障害者サービス、アクセシブルな出版物も含め、読書環境の整備を推進することは、素晴らしいことです。ただ、やはり法律の表現はあいまいで具体性がありません。この第二期基本計画では、着実に推進するための施策があげられています。
図書館等における製作の充実、読書バリアフリーの普及・推進、製作するための書籍データを出版社からご提供いただく試み等、条文ごとに具体的な方向性を定めています。そして、第二期基本計画では第一期基本計画にはなかった、「基本施策に関する指標」を設けたことが大きな特徴です。「第9条関係 公立図書館等におけるアクセシブルな書籍等の冊数」「第11条関係 出版社から公立図書館及び学校図書館、点字図書館に提供されたタイトル数」など、14の指標を設定しました。
法律に則って整備を進め、製作すると同時に、利用者自身もさまざまなアクセシブルな書籍で読書して欲しいと思っています。実は晴眼者にも需要が大きいオーディオブック市場は拡大していますし、テキスト読み上げの電子書籍も多くなってきました。電子書籍を利用する際に必要となるスマートフォンの操作についても、図書館が支援しますので、ぜひ挑戦していただきたいです。
文部科学省、厚生労働省、経済産業省が行政の壁を越えて取り組むこの施策が充実し、すべての国民が読書を楽しめるように全国の関係機関と協力し、進めていきたいです。