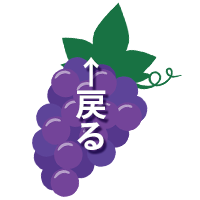ニュースレター「通信あけのほし」
当館支援者向けに年4回、ニュースレター「通信あけのほし」を発行しています。
※ご支援については「ご支援のお願い」をご覧ください。
ニュースレター「通信あけのほし」には以下の内容が収録されております。
巻頭言
理事長・館長からの巻頭言が掲載されています。
お知らせ
当館からのお知らせが掲載されています。
職員レポート
ロゴス点字図書館の職員が参加した委員会や研修会のレポートが掲載されています。
新収図書目録
新しく収めた点字・CD図書の目録が掲載されています。
事業報告(夏季発行号のみ)
法人・図書館の事業報告が掲載されています。
新着情報一覧より、「通信あけのほし」各号の巻頭言がご覧いただけます。(一部メンテナンス中)
新着情報一覧は「こちら」からご覧いただけます。